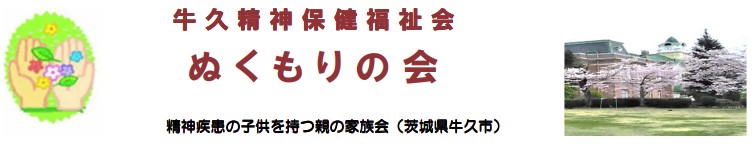|
【はじめに】
過去に開催した勉強会や講演会、及び書籍等から大切だと思われる要点を整理して掲載しました。
ここに記した内容を参考に、統合失調症等の精神疾患や薬のことについて詳しく理解し、当事者様を抱える皆様のお役に立てて頂くことを願っております。
また、定例会で学習した内容も「ぬくもり通信」に掲載していますので、併せて参考にしてください。
「医療法人崇徳会 田宮病院 院長 渡部和成氏」の講演会・本の要約から抜粋
【統合失調症の理解】
統合失調症という病名は・・・
「統合」・・・心や行動をまとめること
「失調」・・・うまく行っていない
「症」・・・・状態。 状態は、水が氷になるように、或は水が水蒸気になるように変化する。
∴ 統合失調症は良くなると言える。希望を持つ事により頑張る力がでる。
【統合失調症の治療目標】
◆患者が病状をうまく管理し孤立せず社会に参加し、自然な笑顔で自分らしく生きら
れる様になる
ことである。
同時に家族も人生の幸せを感じられるようになることである。
◆心の病気は全て慢性疾患なので、急性期であろうと慢性期であろうと、治療においては常に患者は
受け身ではなく主役である。
◆病院は、患者を医療の中心におき患者の視点からの医療を展開していくこと。
患者の病からの回復と幸せの実現に向けて、人生の伴走者として患者に寄り添い援助していく
治療をすることを方針とすべき。
◆だから、患者と家族は、以下のように考えて治療を続けよう!
・焦ってはいけない!
・諦めてはいけない!
・嘆いてはいけない!
・自分だけで何とかしようとしてはいけない!
回復(社会参加)に向かって、患者の仲間や家族に支えられながら、自分のペースで家族と一緒に
一歩一歩進んで行ければ良い。
【統合失調症は、脳と心の病気】
◆脳の病気
統合失調症とは、脳の前頭葉・側頭葉・大脳辺緑系などの部位で機能異常が見られ、ドーパミンと
いう神経伝達物質の脳内での働きの異常がある病気である。(ドーパミン仮説)
しかし、その機能異常を引き起こす原因はよく分かっていない。
◆心の病気
・陽性症状・・・・・・・・幻聴・妄想・興奮(大脳周辺緑系の症状)
・陰性症状・・・・・・・・意欲低下・ひきこもり(前頭葉の症状)
・認知機能障害・・・・・・注意力・判断力・記憶力・計画能力などの低下
・抑うつ症状・・・・・・・気分の落ち込み、絶望
◆統合失調症は、症状的には幻聴・妄想・滅裂・興奮・引きこもり・意欲低下・社会性 低下などの
心と行動の異常が見られる心の病気と見ることができる。
つまり、統合失調症では、脳の病気としての前頭葉や大脳周辺緑系などの機能異常の結果とし
て、心の病気としての知覚や思考の異常(幻聴や妄想)や、心や感情の変化・行動の異常現象(
猜疑的・攻撃的行動・引きこもりなど)が症状として現れる。
◆統合失調症の治療では、
・「心の病気」の側面から、病気を管理し症状にうまく対処できれば、自分らしく生けて大丈夫
だと希望を持たせることが大切。
・原因不明の「脳の病気」のため、「昨日も今日も明日も統合失調症である」ことを忘れず、油断
せず回復を助けてくれる薬を飲み続けることの大切さを理解させる事が重要である。
◆統合失調症の症状は、
・一言で言うと「社会性の低下」という事ができる。
患者によって陽性症状が強かったり、陰性症状が強かったりして、まちまちであるが、「認知
機能障害」はほぼ全ての患者に共通しており、統合失調症の基本症状である。
・認知機能の回復は、薬だけでは得られず、病識を持ち症状を管理し、積極的に社会参加をして
いく中で図ることができる。 私の病院が行う教育入院で、神経認知と社会認知が改善する事
が分かっている。
※「教育入院」とは、急性期の入院を要する患者と病識の無い慢性通院患者を対象に、6週間の
中で患者及び家族の心理教育等を通して、統合失調症は回復可能な病気である事を確認し、
病状管理法や対処法を学ぶ。
|
■ 統合失調症をはじめとする抗精神病薬の基礎知識 ■
|
<講師> 牛久南薬局 管理薬剤師 吉田雅光氏
統合失調症は、脳の神経伝達物質の異常が原因とされている。
生まれつきの素因と社会的な要因の相互作用により神経伝達物質のバランス異常をきたして発症する。
・約100人に1人の割合で発症(人種や性別によってこの割合が変わることはない。)
・16歳から40歳と比較的若い世代での発症が多い。
・陽性症状 :幻聴・幻覚・思考伝播・妄想等。
・陰性症状 :感情の平板化・意欲の低下等。
・症状の経過 :不眠・イライラ感→不安・興奮。
・症状と社会生活 :認知障害・不安抑鬱症状。
・対処方法 :薬物療法+心理社会的治療。
薬は何故必要か? 薬は活発になり過ぎた脳の働きを休める役割を担っている。
・薬の継続で、症状の再発を予防している。「指示どおりの服用」が大切:薬を中止すると1・2年の
内に80%以上が再発すると言われている。
・薬を服用せず再発した時は、症状が悪化し薬の調節が難しくなる。
・「副作用」が起こったら、自分の判断で服用を中止せず、医師・薬剤師・看護師に相談する。
・抗精神病薬は中脳辺縁系神経路と中脳皮質神経路の神経伝達物質であるドパミン・セロトニンの量を
調整する作用をもっている。
・抗精神病薬は、常用量では催眠・麻酔作用を有さず、身体や精神依存も示さない薬だから、安心して
服用して欲しい。
抗精神病薬の分類と種類:第1世代(定型)と第2世代(非定型)の薬。
定型薬 :陽性症状を改善する。錐体外路系副作用出やすい。
非定型薬:(陽性症状+陰性症状)に効果。
※錐体外路系副作用少ないが1部の薬剤では、体重増加・血糖値上昇に注意が必要。
抗精神病薬の特性による薬剤選択:薬剤は、第Ⅰ群から第Ⅳ群に分類される。
(第Ⅰ群〜第Ⅲ群は第1世代の薬、第Ⅳ群が第2世代の薬)
現在では、副作用の低減や陰性症状に対する効果が期待できる第2世代(第Ⅳ群)の薬が第一選択薬
として位置づけられている。
第1世代の薬もその特性に合わせて、以下のような症状に使用されている。
・精神運動興奮が強い場合 :催眠作用が強いⅠ群の薬
・幻覚・妄想が強い場合 :異常体験抑止作用が強いⅡ群の薬
・再発防止の場合 :Ⅱ群薬の作用を持ちながら催眠作用の弱いⅢ群の薬
・抗精神病薬と併用される薬剤 :副作用に対して併用される薬;抗パーキンソン病薬・下剤
・統合失調症の随伴症状に対して併用される薬:抗不安薬・睡眠薬・抗うつ薬
新しい薬への切り替え:少なくとも4週間、3カ月以上要することもある。
・前の薬の離脱症状や新しい薬で起こる副作用に注意しながら進める必要がある。
・薬の剤型(液剤・錠剤・注射液)や回数については、医師・薬剤師・看護師に相談する。
薬と嗜好品との関係:酒は基本的に禁止。
タバコは薬が効きにくくなることがある。
コーヒーはカフェインの覚醒作用と糖分摂取が問題。コーラも糖分が多く、飲み過ぎに注意が必要。
多くの人が回復しています!
家族は、
・病気についての正しい知識を持ちましょう。
・ご本人の感覚を理解しましょう。
・地域の人と情報を交換しましょう。
・毎日の服薬や治療の手助けをしましょう。
・焦らずにゆっくりと見守りましょう。
ジェネリック医薬品について:抗精神病薬の場合、第1世代(定型)の薬にのみジェネリック薬が有るが値段の差
が小さく、精神科の医師はジェネリックへの変更を好まない場合が多く、あまり採用されていないのが実情。
【質疑応答】
◆薬の服用について
気分が悪くなり、飲まなくなって通院もやめている人が多い。
不調の様子をしっかり伝えて、医療側に対応してもらうことが肝要。
薬の継続服用は、症状が安定していても、再発防止のために必要です。
◆コーヒーについて
砂糖を入れないでミルクだけにすると良い。
血糖の検査は病院でしてくれる。
◆本人が薬を飲めない場合
注射(デポ剤)があり、効果が長く続き、通院の回数、注射の頻度を減らす利点がある。
医師に相談してください。
◆服用時間に寝ている場合、服用の時間は多少ずれてもよいから、寝かせておいた方がよいと思う。
◆薬切り替えの場合、単剤の時と複剤の時とでどちらが変えやすいか?
複数の薬の内1種を替えたり減らしても余り変わらないと思うが、医師と相談してください。
<講師> 水海道厚生病院 河合院長
【なぜ、今、『減薬なのか』】
・厚生労働省が今年4月に減薬のガイドラインを発表した。
多剤大量処方がなかなか減らない為、診療報酬を引き下げる通達が出た。
・厚労省の保健局医療課が発表した診療報酬改定の概要の中で、適切な向精神薬の使用の推進
として多剤大量処方の規定が書かれている。
→1回の処方において3種類以上の抗不安薬及び睡眠薬、4種類以上の抗うつ薬又は、抗精神
病薬を投与した場合を言う。
・なぜ日本で「多剤・大量処方」が行われたのか?(国際的にもおかしいとの見解)
①多剤併用の漢方医学が影響していると思われる。
②日本は国民皆保険制度のため薬を多く処方しやすい。
【問題点を解決するために】
・統合失調症の病気と特徴を学ぶ(内容省略)
・治療の歴史を学ぶ
1950年過ぎに薬物療法が開発された→陰性症状を抑えるため大量処方の時代
2000年位からシンプルな処方の推奨
・非定型薬(錐体外路症状を軽減した薬)の開発と治療
【適切に用いれば種々の利点】
・錐体外路症状が少ない
・抗パーキンソン薬を減らせる
・抗コリン性副作用(便秘など)が少ない
・陰性症状、認知機能を悪化させない
飲みやすい→治療維持しやすい→再発を防ぎやすい
−大量に使っては意義が少ない
−大量の従来型と併用しても意義が少ない
−すでに何度も再発し、慢性化・難治化している場合
①新薬の一般的な使用料では症状を抑えきれないことが多い
(通常用量の2倍程度は必要なことがある)
②新薬のも1種類では足りず2種類程度まで併用が必要な場合があるだろう
③新しい抗精神病薬よりも、旧型の薬の方が良い場合があるかもしれない
【減薬のメリット・デメリット】
<メリット>
・種々の副作用が軽減する
・精神症状が改善するかも知れない
・治療を維持しやすい→再発を防ぎやすい
<デメリット>
・薬を変えれば、別の副作用が出現することもある
・精神症状が悪化するかも知れない→元に戻らない恐れ
【大量処方かどうかの目安】
・抗精神病薬をCP(クロルプロマジン)換算で1日、1,200mgまでは許容量と思われるが、
多い人で3000mg〜6000mgという人もいる。
・3000mgを超える量は止めなければならない。
・『減量は難しい』
〜離脱症状が起こりやすい。
・抗コリン性離脱症状嘔気、嘔吐、下痢など胃腸症状、不眠、発汗、頭痛、めまい、不安、
焦燥など
・超過敏性精神病
・離脱性錐体外路症状
反発性アカシジア、反発性パーキンソニズム、離脱性ジスキネジア
【まとめ(結論)】
すべての患者さんにとって、"単剤化"や教科書的な"通常用量"がベストであるとは限らない。
|
■ オープンダイアローグが教えてくれるとっても大切なこと ■
|
「筑波大学教授 斎藤環氏」のこんぼ亭DVD等から抜粋
【オープンダイアローグとは】
Open Dialogue(開かれた対話)とは、フィンランドの西ラップランド地方にあるケロプダス
病院を中心に1980年代から実践されてきた統合失調症のケア技法/システム/思想である。
◆治療チームは危機にある当事者の自宅に赴き、危機が解消する迄の約2週間毎日会い続ける
◆変える・治す・決定することではなく、対話を続け・広げ・深めること
尚、議論や説得は問題をこじらせるため絶対にしないこと
◆治療プロセスに当事者や家族を巻き込み、短期間の研修を受けたセラピストチームが対応する
◆チームで詳しくちゃんと聞く。(幻聴や妄想は改善する)但し、聞き方に工夫がいる
◆服薬や入院は可能な限り行わない(薬を使用する場合は、不要なものは使わない)
◆リフレクティングの発想で行う
・評価や意思決定は、本人や家族の前で行う
・治療方針を話し合う姿を本人や家族に見て貰う
・アイデアを「お盆に載せ」気に入ったものを本人が自発的に選ぶ
◆西ラップランド地方における2年間の予後調査結果から、
抗精神病薬の使用率が35%(100%)、
2年間の再発率が24%(71%)、症状の残遺率が18%(50%)、
障害者手当の受給率が23%(57%)
に低下し、世界最高の結果を出すに至った。(括弧内は、伝統的治療群の割合を示す)
【治療に於いて大事にしたい5つの要因(SPORN)】
①S(Space) ・・・・・・ 心のスペース(居場所)
②P(Pace) ・・・・・・ 自分に合った回復のペース
③O(Opportunity) ・・・ (機会)不確実性の耐性
治療プランを立てずにひたすら対話に打ち込んでいく
④R(Route) ・・・・・・・ 通過点。失敗するリスクを冒す権限を本人任せにする
⑤N(Narrative) ・・・・ 回復してきたストーリーを自分で考える、自分なりに解釈する
|